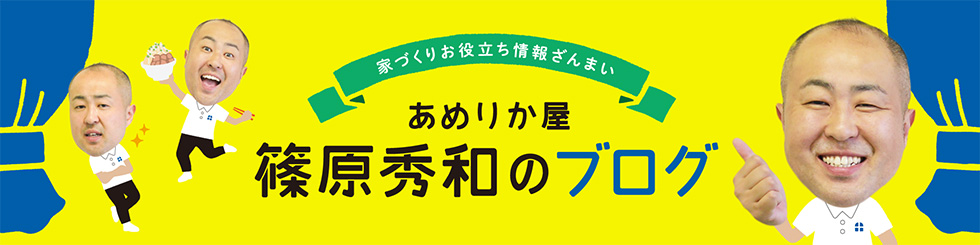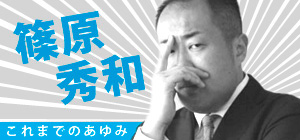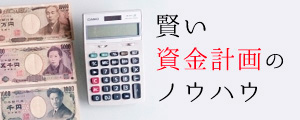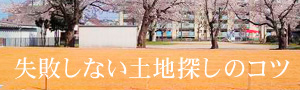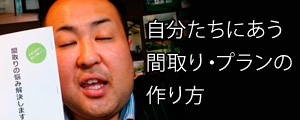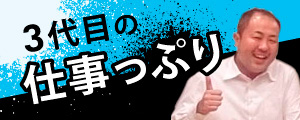地鎮祭の準備やマナー
おはようございます。福井県敦賀市の建築会社あめりか屋の失敗しない家づくりアドバイザーの篠原秀和です。今日もよろしくお願いします。
消費税増税前ということがあり、住宅の着工数が全国的に伸びているそうです。先日も神社さんへ地鎮祭の日程調整の連絡をしたところ、1時間きざみで予約が入っているとのことでした。
今日はそんな地鎮祭についてよくあるご質問を元に、記事をまとめてみますね。(福井県敦賀市でよくある地鎮祭というものをベースに書いてますので、詳しくはその会社さんへ聞いてみてくださいね。あくまでだいたいの概要という感じで思っておいてください。)
地鎮祭とは?

工事をスタートする前におこなう祭事ごとで、土地の神(氏神)を鎮め、土地を利用させてもらうことの許しを得るということです。ほとんどの新築工事の時におこなうのが慣例をなっています。工事の無事をお客さま・工事関係者のみんなでお祈りするというイメージでしょうか。
地鎮祭を行うことになれている人はあまりいないので、誰しも初めての人がほとんどです。ですので、分からないことが多いのは当然のことなんです。ご安心ください。
①なにを準備すればいいの?
テントや、竹や縄などの会場の設営は工務店やハウスメーカーが行います。
お酒(神酒)や乾杯用つまみ(するめ・昆布など)も工務店やハウスメーカーで準備です。
お供え物(海のもの・山のもの)は、神主さんもしくはお客さま(お施主さま)が準備をすることになります。敦賀の神社さんですとだいたいが神主さん側で準備をしていただけます。
すなわち、お客さまは、玉串料(初穂料とも言います。神主さんへおさめるお金)のみをお持ちしてもらうというケースが一般的です。
玉串料に定価はありませんが、だいたい2~3万円あたりだということだそうです。それ以外に、工務店に支払う費用や祝儀などは必要ありません。式が終わった後に神主さんへお渡ししてもらえればいいかと思います。
②どんな服装をすればいいの?
どんな服装でも基本的には構いませんが、あまりラフな服装は避けたほうが無難かもしれません。もちろん正装(スーツやシャツスタイルなど)がベターですけどね。
③他にはどんなことを気にすればいいの?
地鎮祭の最中では、
・玉串奉奠=草のようなものを神棚におさめて礼をする。
・地鎮の儀=「えい、えい、えいっ」と言って草を刈るしぐさをします。
などの儀式がありますが、それは当日、神主さんや工務店さんが教えてくれます。予習するほど難しいものではありませんので、ご安心を。
出席者は誰が参加するのかは、お住まいになるご家族はもちろん全員来ていただきたいですし、お祝いごとでもありますので、ご両親をお呼びするということも多々あります。基本的には誰が来てもらっても構いません。ただ、参加人数は乾杯用のお皿など細かい準備があいますので、事前に工務店さんへ伝えておいた方が良さそうです。
地鎮祭が終わったあと、建物位置の立ち会い確認をしてもらうケースが多いです。敷地境界や道路からの離隔距離の確認などをしてもらいます。
それとあわせて、工務店の方で近隣挨拶(工事が始まれば、騒音や駐車などで近隣の方にご迷惑をおかけするので近隣の方へご挨拶をするんです。)をするということもありますが、お客さまも一緒に行った方がベターではありますが、工務店だけで行くケースも多々あります。あくまで気持ちの問題ですが、工務店さんと相談してみるといいでしょう。
ということで、地鎮祭は経験が無いだけで、難しいことではありません。
もし分からないことがあれば、工務店さんに聞いてもらえれば解決すると思いますよ。
あなたの家づくりにお役立ちすることを願って・・・。
最後まで読んでいただきましてありがとうございました!!(^^)
--------------------------------------------------
株式会社あめりか屋(木造住宅の新築・リフォーム、店舗・事務所の新築・リフォーム)
福井県敦賀市長沢13-13-1
3代目一級建築士
失敗しない家づくりのアドバイザー
篠原 秀和(しのはら ひでかず)
facebook・twitterやってます。ぜひお友達になってください。
--------------------------------------------------
篠原秀和(シノハラヒデカズ)ニックネームはシノハラ(カタカナで。笑)
株式会社あめりか屋 代表取締役
一級建築士・住宅ローンアドバイザー
1977年6月23日生まれ
福井県敦賀市在住
2000年に日本大学卒業後、20代の頃は大手ゼネコンにて設計職と施工管理職を経験し、あめりか屋3代目として2007年から勤務。2011年頃から本格的に住宅事業を担当するようになり、業務は営業というか楽しいステキなお家づくりのプロデューサーをしています。
また自身のブログは2013年4月から毎日更新中。
・・・というマジメな仕事ぶりとはまた違った一面を持っていて、SNS(Instagram、twitter、Youtube、Facebook、TikTok)では楽しくてクスっと笑える投稿を日々発信中。ぜひフォローしてやってください。