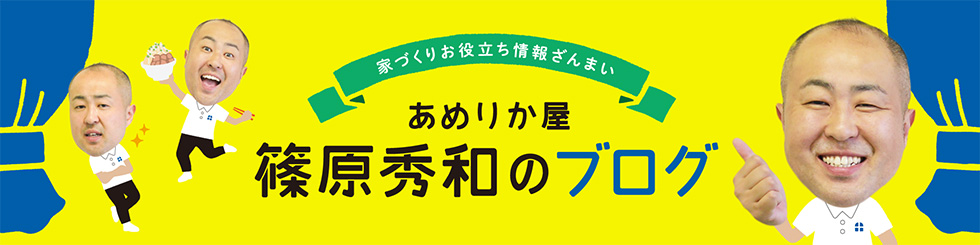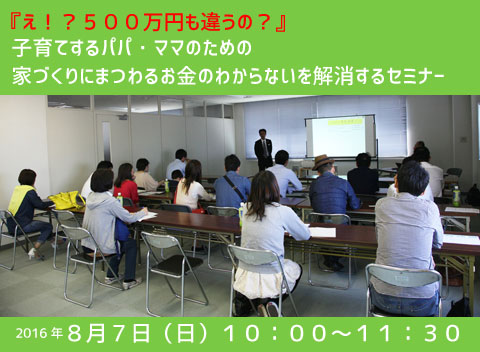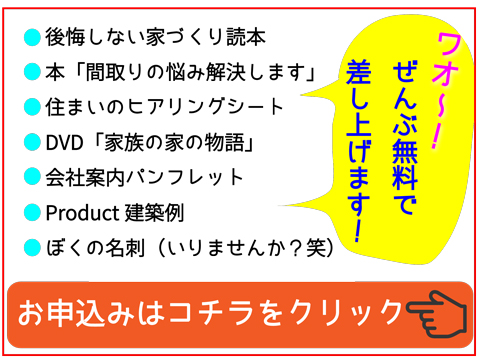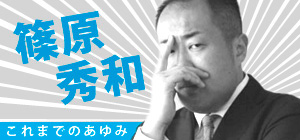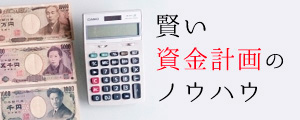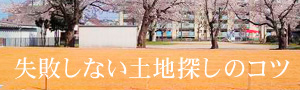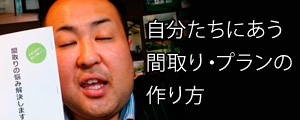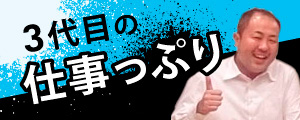三隣亡に建築すると大凶だ!という話があるとかないとか
こんにちは!福井県敦賀市の建築会社あめりか屋のこだわりの注文住宅専門家の篠原秀和です。
☆あめりか屋施工事例←ぜひごらんください☆
地鎮祭や建て方の日にち
工程を決めていく中で、地鎮祭や建て方(建前、棟上)の日にちは大事です。
その日が工事を進めるにあたっての目安・区切りになりますし、お客さまはじめいろんな人がからみますからね。
ですので、いつも1~2ヶ月前には決めます。「え~っと、じゃあ明日やります」っていうもんじゃないしね。笑
ということで日にちを決めるわけですが、よくみなさん言うのが「大安」を選んで「仏滅」は避けるという慣習がありますよね。
しかし、大安を選んでおけばいいってもんでもないんです。実は。
地鎮祭や建て方をしないほうがいいという日があるんです。
それが・・・「三隣亡」です。
三隣亡とは
三隣亡とはなんなのでしょうか?
三隣亡は少し前までは建築関係者の大凶日とされ、棟上げや土起こしなど建築に関することは一切忌むべき日とされた。その字面から、この日に建築事を行うと三軒隣まで亡ぼすとされたためである。現在でも、棟上げなど建築に関することの凶日とされ、建築関係の行為は避けられることが少なくない。「高い所へ登るとけがをする」と書いている暦もある。
wikipediaより
え?
三軒隣まで亡ぼすとか!!!
なんだそれ、こわいな~、こわいな~。
ようするに、ぼくらはこの三隣亡は避けて地鎮祭をしたり建て方したりするようにしています。(引越しなんかもダメとか言われてますよね)
そんなの迷信だけどね
でもこれは根拠が確定している科学的なものじゃありません。
ぼくらのような工務店なら三隣亡は避けて日取りを決めることが多いけど、量産型ハウスメーカーさんだと「三隣亡?は?そんなの迷信でしょ?」というところもあり、全く無視する住宅会社さんだってあるようです。
はっきり言って迷信でしょ?というのはぼくも賛同しますし、読んでいるあなたもそんなの迷信だしどうでもいいよね・・・と思われるかもしれません。
でも三隣亡にわざわざしなくてもいい
ただ、でも、「じゃあ人生に一度のマイホームの建築の日を、三隣亡の日にちに合わせましょう」という人はほぼいません。
三隣亡というものがあって、日にちはどうしますか?避けますか?と聞くと、みなさん「そんなの迷信だ」と思いながらも、まぁそんなのがあるなら避けておこうか・・・となりますからね。
年に30日弱しかないので、日程調整すればぜんぜん避けられるもんですし。
最後に
ま、だから、こうしてブログに書いてるし、日にちを決めるときに「三隣亡」にかかっていたらちゃんとご案内して、判断してもらいます。
若いお客さまは知らないケースも多々ありますし、三隣亡のことをお伝えすることなく完全に無視してやってしまった場合、お客さまがもしも後からそれを知ったら不安になるかもしれませんしね。
そんな不安ぜんぜんいらないよね。
っていうことで、三隣亡の話を一切してくれない住宅会社さんで建てる場合、このブログを読んで心配になった場合は「三隣亡 いつ」「三隣亡 カレンダー」で検索して、日にちを調べてしてみてくださいね~。
↑クリックするとセミナーの詳細のブログが開きますよ~。ぜひチェックしてみてください^^
【あわせてこんな記事もおススメ】
※ 鍵を玄関の下駄箱の上などの見えるところに置いちゃダメだよ。
blog⇒敦賀市の工務店で注文住宅の新築・リフォームするならあめりか屋篠原秀和のブログ
~今日の体重=84.7kg(-0.2)~
篠原秀和(シノハラヒデカズ)ニックネームはシノハラ(カタカナで。笑)
株式会社あめりか屋 代表取締役
一級建築士・住宅ローンアドバイザー
1977年6月23日生まれ
福井県敦賀市在住
2000年に日本大学卒業後、20代の頃は大手ゼネコンにて設計職と施工管理職を経験し、あめりか屋3代目として2007年から勤務。2011年頃から本格的に住宅事業を担当するようになり、業務は営業というか楽しいステキなお家づくりのプロデューサーをしています。
また自身のブログは2013年4月から毎日更新中。
・・・というマジメな仕事ぶりとはまた違った一面を持っていて、SNS(Instagram、twitter、Youtube、Facebook、TikTok)では楽しくてクスっと笑える投稿を日々発信中。ぜひフォローしてやってください。