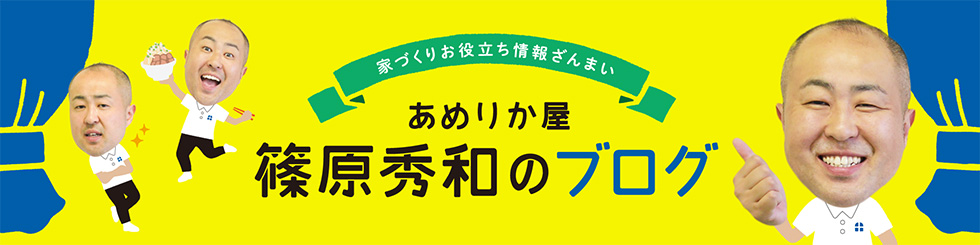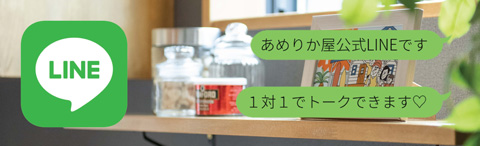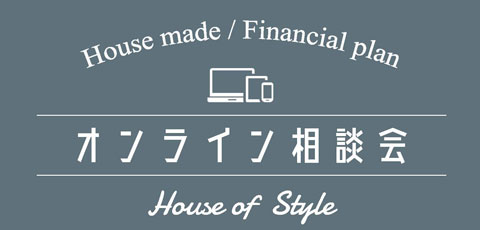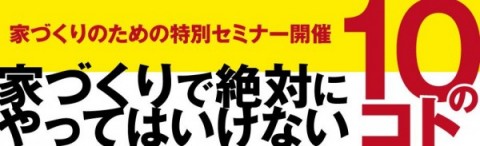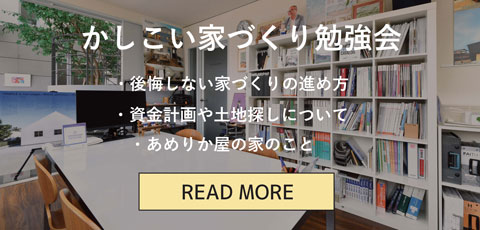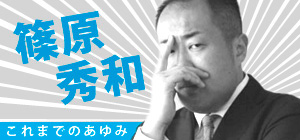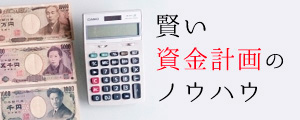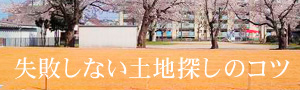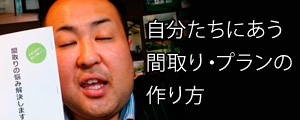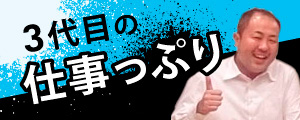子ども部屋を無駄なく使うための3つのポイント
家の中で使い方が変わるスペース
家は建てる時、間取りを考える時、「この部屋はどう使おうか」「あのスペースはどう使おうか」と頭を巡らせるものです。
ただいくら考えても、家の中で今と未来では使い方が変わるものと変わらないものがあります。
玄関、お風呂、キッチン、リビングなどは使い方って変わらないでしょうが、子ども部屋となるとかなり使い方が変わります。
子ども部屋の使い方
だいたいのイメージですが・・・
0歳~7歳:普段の生活も寝るのも親と一緒なので、ほぼ使わずに空き部屋となっていることが多いですね。
7歳~10歳:小学校に入るとぼちぼち使われるようになりますが、一人で寝たり勉強したりとまでは使われない傾向です。(ご家庭によりますが)
10歳~18歳:ようやく子ども部屋を子ども部屋としてフルに使うようになります。勉強はリビングでするという子もいるでしょうが、寝たり、片付けしたりと自立にむけた生活空間として使われるはずです。
18歳~:大学に行ったり、就職したりと、そもそも自立して家を出るケースもありえるので、子ども部屋が再度空き部屋、または物置状態になっているというのもよくある話ですよね。
無駄をなくしたい
という感じで、子ども部屋の使い方は変わるものなんです。
子ども部屋はできればいい部屋をあてがってやりたい・・・と思うのも親心ってなもんですが、なにかとコストのかかる家づくりですし、無駄もなくしていきたいですよね~。
だからこそこの子ども部屋の使い方が変わるという前提を把握して、子ども部屋も無駄なく使っていくためにポイントをいくつかあげていきます。
北側の小さい部屋でいい
まずは北側の小さい部屋(4.5帖とか)でいいということですね。
・使い方が変わるのでまともには10年くらいしか使わないから
・子ども部屋にこもってほしくないから潤沢な部屋じゃなくていい
などの理由で、子ども部屋を南側の大きな部屋(6帖以上)という「好条件」にしすぎないということですね。
大きな1部屋にしておいて、後でわける
続いては、2部屋を大きな1部屋にしておいて後で間仕切り壁を作って2部屋にできるようにしておくということですね。
・子どもの成長にあわせて最適なスペースを作りやすい。
・子どもが小さい頃は家族みんなでこの大きな部屋で寝ることができる。
などの理由で、可変性を持たせるということもポイントです。
「子ども部屋」という呼び名をやめる
最後に「子ども部屋」という名前をつけないということです。
これは物理的なことよりも考え方に近い話ですが、うちでは最近子ども部屋という名前の部屋をつくっていません。個室AとかROOM Aとかそんな名前の部屋にしています。
理由としては、子どもの成長にあわせてその部屋を誰が使ってもいいというメッセージでもあります。
子どもが幼い頃、子どもが巣立った後、ご主人の書斎にしていてもいいわけですもんね。
最後に
以上3つのポイントをあげてみました。
ただし、この3つが正解!というわけでもありません。ご家庭それぞれの考え方、年齢、育ってきた環境なども相まっていろんな選択肢がありますしね。
そして、その選択は基本的にご夫婦でするものです。
ですので選択してもらいやすいように、ぼくはブログでこうして書いているので、ぜひご夫婦で相談してくださいね~。
他にも聞きたいことあればなんでも聞いてくださいね~~。お気軽にどうぞ~~。
~今日の体重=90.8㎏(-0.3)~
篠原秀和(シノハラヒデカズ)ニックネームはシノハラ(カタカナで。笑)
株式会社あめりか屋 代表取締役
一級建築士・住宅ローンアドバイザー
1977年6月23日生まれ
福井県敦賀市在住
2000年に日本大学卒業後、20代の頃は大手ゼネコンにて設計職と施工管理職を経験し、あめりか屋3代目として2007年から勤務。2011年頃から本格的に住宅事業を担当するようになり、業務は営業というか楽しいステキなお家づくりのプロデューサーをしています。
また自身のブログは2013年4月から毎日更新中。
・・・というマジメな仕事ぶりとはまた違った一面を持っていて、SNS(Instagram、twitter、Youtube、Facebook、TikTok)では楽しくてクスっと笑える投稿を日々発信中。ぜひフォローしてやってください。